【九州産業大学】英語の傾向と対策(勉強法)です。
九州産業大学の英語の傾向
例年、大問4題に解答時間は60分で行われます。問題構成として、長文読解(内容一致選択)、会話文・慣用表現(空所補充)、文法問題が2題(空所補充、英文整序問題)となっています。
九州産業大学の英語は、スピードとある程度の読解力が必要となります。ジャンルは、歴史・言語・コミュニケーションを中心に多岐にわたります。時事問題を話題にしたものを時折、出題されるので、ニュースには日ごろから敏感になっていたいですね。
九州産業大学「英語」の対策・勉強の仕方
特に、
- 整序問題
- 長文読解
が合否を分けるので、しっかりとした対策が必要です。
九州産業大学の整序問題
整序問題は、うすいテキストを1冊仕上げておくことをおすすめします。ある程度、出題パターンが限られるので、その量はありますが、体で覚える領域(条件反射で解ける)まで何度も繰り返してやりましょう。
おすすめのテキスト 大学入試 門脇渉の 英語[整序問題]が面白いほど解ける本
九州産業大学の長文読解
勉強の材料は、共通テスト過去問、九州産業大学の過去問、その他の福岡大学、中村学園大学の過去問も余裕があればやるということになるでしょう。英文の難易度は難しく、またしっかりとした読解力が必要となります。
しかしながら、本文の内容一致問題はその周辺の読んだら、解けたり、傍線部解釈も、語彙力を聞く問題だったりするので、こういうところでしっかりと得点していきたいところです。
特に重点的に学習したいところは、熟語と準動詞(不定詞・動名詞・分詞・分詞構文)、関係詞、比較、動詞の語法、時制、仮定法あたりでしょうか。これは、文法問題を解くときにお役立ちます。

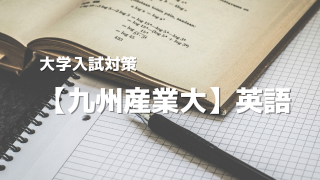
コメント